読書冒険マラソンの第5作目です。
1冊目(五十音順じゃない)、2冊目(五十音順最初の作家さん)ときて、3冊目はまた五十音順ではなく、4冊目も五十音順ではなかったです。
5作目は五十音順になりました。
選んだのはこの本です。
『同志少女よ、敵を撃て』
著者:逢坂冬馬(あいさか とうま)
発行年:2021年11月
発行所:早川書房
492ページ
分類番号:913.6ア
この本を選んだきっかけ
読書冒険マラソンは上述したように、れんげの図書館にある作家さんを五十音順に全制覇する計画です。
本棚に行って見ると五十音順の一番最初は愛川晶さんで、その次に並んでいるのが逢坂冬馬さんでした。
二冊しか並んでいなかったのですが、この『同志少女よ敵を撃て』は出版当時何かの賞の候補になって話題になっていたので覚えていました。
表紙の少女のイラストが印象的でした。
一目見たら忘れられないインパクトを感じていたので、借りてみました。
感想
舞台は第二次大戦時、ソ連に実際にいた女性の狙撃兵たちの話。
主人公セラフィマは故郷を敵であるドイツ兵に焼かれ大切な人たちを無残に殺され、復讐のために狙撃兵となる。
そして戦いの中で、自分の信念を培ってゆく。
第一印象
読む前の印象は”戦争の話だし、ちょっと重そう””女性が戦争に加わらなきゃならなくなって、つらい思いをするのでは”というものでした。
つらくなったらいやだな、と思っていました。
一転、読み始めて最初の印象は「キャラが二次元的ですぐにアニメになりそう」というもの。
戦う少女スナイパー、同僚に元貴族の美少女。
美しく残酷な上官、大学生の美少年スナイパー、背が高く痩せた宿敵。
口も態度も悪いが根はいい奴とおっとりとやさしい仲間。
いい感じだった幼馴染(後に再会する)。
などなど。
戦争は別として、主人公たちの関係性や話の筋書きははエンターテインメントになっていると思った。
アニメのビジュアルがぱっと想像でき、物語を読み終わるまで楽しめた。
ちなみに主人公の直属の上官の声のイメージは榊原良子さん(ナウシカのクシャナ王女の声)。
戦争の始まり
戦争をしないことは理想。
戦争はだれも望んでいないはずだ。
なぜ戦争は起こるのか、なぜまじめでやさしい人が人を殺したいと思うのか。
だが実際に目の前で家族や親しい人たちが無残に殺され凌辱されるのを見たら、人は殺した相手を許すことはできないだろう。
復讐を遂げるという目標によって生きる理由が生じ、過酷な戦闘を戦う意義が生まれる。
もともとは人は喜びを持って生きていたのに。
生きる動機が復讐に変わる。復讐が生きる希望を与えてくれる。そんな状況。
なぜなら戦争中は生きるか死ぬかしかないから。
戦争中は人殺しが生きる目標になってしまうという状況に、読んでいる私も飲み込まれた。
そもそもじゃあ戦争はなんで始まった?戦争って何?という疑問が生まれた。
国と国が争う。
でも「国」はどこにあるのだろうか。「国」の意志はどこにあるのか。
国とは、一人一人の集まりなのに、戦争を始めるという明確な意思はセラフィマたちのものではなかったはずだ。
否応なく巻き込まれてゆく戦争というものは、実体がないぶん恐ろしいと思った。
始まってしまうと自動的に戦いが続く。
戦いの中に日常が追いやられていく。戦いが日常生活になる。
どちらが悪いのかは関係なくなりただ自分たちを守るために戦い続ける。
戦っているときはもはや正義はなくただ戦いがあるだけ。
まるで戦うために戦っているようだ。
そんな現実的な日常が描写されていた。
それを読んでいるこちらも、歴史的背景や国の意志など関係なくなり、ただ主人公たちが憎しみに身を投じていくのを追いかけることになる。
戦争はそれぞれの中にある
主人公の上官のイリーナが、主人公の少女たちに問う「お前はなんのために戦うのか」という問いは、だからこそ意味を持つのだと思った。
戦うことしか許されない状況でときに自分を見失いそうになる少女たちにとって、その質問の答えを考えることが、人間としての心を守るために必要だったのだと思う。
その答えは一人一人の中にある。戦争はそれぞれその人の中にある。
そしてセラフィマの戦争とは。
セラフィマの敵は
国と国との戦争で敵と言えば相手の国。
当然敵は相手国の兵士。
だがセラフィマの敵は厳密にいうと違った。
戦争に乗じて行われる虐殺、暴行などの犯罪行為。
戦争自体が許されない暴挙だがそれに乗じて行われるそのような行為は最も愚かで下劣だ。
そしてそれらは兵士がほぼ男であるため男によって行われる。
なぜ人は戦争で奪った領地を蹂躙し市民を虐殺することをやめられないのだろうか。
戦時下では普通の神経ではいられなくなるのか。
異常な興奮状態から普段では考えられないことをし、それが許されるかどうかなど考えられなくなる、そんな多くの兵士(男)の姿が描かれる。
対してセラフィマ達女性のロシアの赤軍兵士たちはそれぞれの信念を持って戦う。
その姿が尊いと思った。
セラフィマにとっての敵とは……それは本書をぜひ読んでください!
ひとつ言えることは、セラフィマは私たち女性の同志だ。
女性の怒りのために戦ってくれた。
瑞々しい戦士たち
約一年の厳しい訓練生活の中で、年頃の女子たちは絆を育んだ。
卒業試験に合格し喜びあい友情を確かめ合う彼女たちは戦時下でなければ普通の女子学生だ。
そして一瞬で生死が決まる過酷な戦場で、どう戦うべきか日々考え、ときに同志とぶつかったり、友情を育みながら生きている。
戦うか死しかない毎日でも、その姿はとても瑞々しい。
日常を戦争に奪われていても、青春を生きている彼女たちのそんな姿は、この物語のなかでまぶしい煌めきを感じさせる清涼剤となっていると思う。
同志少女よ、敵を撃て!
ほとんど戦場での話が続くが飽きさせない。
最後のクライマックスに向けては特に読み応え十分で、ハラハラドキドキした。
そして最後の戦いが終わったとき、私は主人公に喝采していた。
自分が定めた本当の敵を撃ったセラフィマ、万歳!
逢坂冬馬さんはこんな人
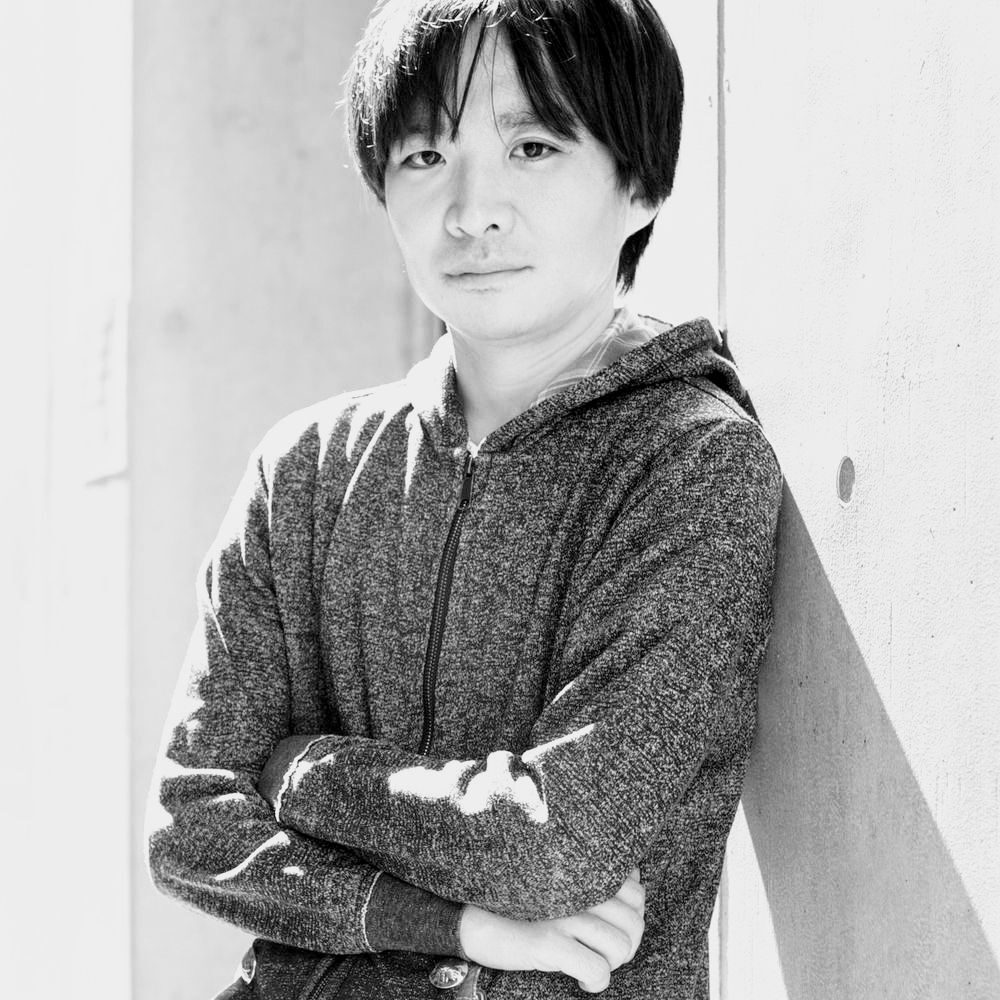
ご本人のSNSより画像をお借りしました
氏名:逢坂冬馬(あいさか とうま)
生年月日:1985年10月8日
出身地:埼玉県所沢市
最終学歴:明治学院大学国際学部国際学科
2021年に『同志少女よ、敵を撃て』が第11回アガサ・クリスティー賞大賞を受賞
同年、第166回直木賞候補作になりました。
2022年、年本屋大賞ノミネート作、ついで第9回高校生直木賞候補作になったあと、本屋大賞受賞。
この作品がデビュー作だなんて!(すごい)
まとめ
逢坂冬馬『同志少女よ、敵を撃て』を読みました。
戦争の戦いの場面の連続ですが、飽きずに読み進むことができました。
特に最後へと続くシーンはページをめくる手が止まりませんでした。
今まで何度も思ったことがありますが、この本を読んで、つくづく私は小説家にはなれないなとまた思いました。
(私の貧相な)予想通りにことは進まず(当たり前)、ハラハラドキドキの末、最後は大喝采でした。
最後までお読みいただきありがとうございました。
